関連記事
お知らせNews
健康情報 命を救うAEDについて知っておこう
公共施設や商業施設などで見かけるAED。 かつては医療従事者に使用が限られていましたが、 2004年から一般の人も使えるようになりました。
あれから約20年。 その間、 AEDにより約8,000人の命が救われています。
AEDの使用で生存率は大幅に高まる
心臓の拍動のリズムが乱れる状態を不整脈といいます。 不整脈にはさまざまなタイプがありますが、中でも突然死につながる危険な不整脈の代表が、 血液を全身に送り出す心室がけいれんするように細かく震える心室細動です。
心室細動が起こったら、 一刻も早く本来の拍動リズムを取り戻す必要があります。 その際に有効な医療機器がAED(自動体外式除細動器) です。
総務省消防庁 「令和5年版救急救助の現況」 によると、 救急車が現場に到着するまでに全国平均で約10分かかっています。 その間に何も救命措置を行わなかったケースでは、1カ月後の生存率はわずか6.6%だったのに対し、 心臓マッサージを行うと約2倍の12.8%にアップ。 さらにAEDで電気ショックによる除細動を行うと50.3%と半数以上が救命されています。
もし、倒れた人がいて意識がなかったら救急車を呼び、 心臓マッサージを始めましょう。 同時に、 周りの人にAEDを持ってきてもらいます。
AEDの使い方は簡単。 指示に従って対応するだけ
AEDは初めての人でも簡単に使えるように設計されています。 機重によって多少の違いはありますが、一般的にはAEDのふたを開け、電源を入れると、 「パッドを胸に装着してください」 といった音声による指示が流れます。 それに従って、倒れている人の胸に電極パッドを貼ると、 電気ショックが必要かどうかを装置が自動で判断してくれます。 AEDが必要と判断したら、 「ボタンを押してください」という指示が出るので、 ボタンを押します。 このとき、倒れている人の体に触らないようにしてください。
使い方は簡単とはいえ、人が倒れた場で冷静な対応はなかなかできないものです。 地域の消防署や自治体などで心臓マッサージやAEDの使い方の講習会を行っています。 これに参加して救命救急の方法を学んでおくと、いざというときに迷わずに行動できます。
AEDの設置場所がわかるマップアプリを活用して
現在、日本全国に約67万台のAEDが設置されています。 一方で、設置台数の割に使用数が少ないという現状があります。 その理由の一つに、 どこにあるのかがわかりにくいことが挙げられます。 日本急医療財団や日本AED財団などが、 AEDの設置場所がわかるマップアプリを配信しています。 家や職場の近所、通勤・通学路にあるAEDの場所を調べておくとよいでしょう (日本救急医療財団: 全国AEDマップ、 日本AED財団: AEDN@VI)。
なお、AEDについてわからないことがある場合には、 薬局の薬剤師に気軽におたずねください。
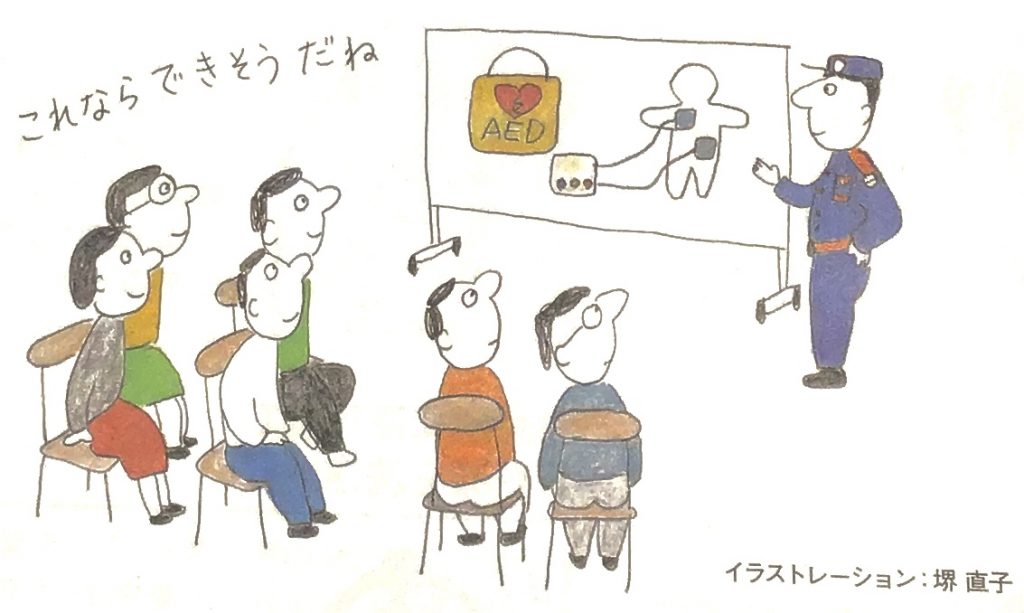
最新の記事
カテゴリー
- アーカイブ
- 2026/02
- 2026/01
- 2025/12
- 2025/11
- 2025/10
- 2025/09
- 2025/08
- 2025/07
- 2025/06
- 2025/05
- 2025/04
- 2025/03
- 2025/02
- 2025/01
- 2024/12
- 2024/11
- 2024/10
- 2024/09
- 2024/08
- 2024/07
- 2024/06
- 2024/05
- 2024/04
- 2024/03
- 2024/02
- 2024/01
- 2023/12
- 2023/11
- 2023/10
- 2023/09
- 2023/08
- 2023/07
- 2023/06
- 2023/05
- 2023/04
- 2023/03
- 2023/02
- 2023/01
- 2022/12
- 2022/11
- 2022/10
- 2022/09
- 2022/08
- 2022/07
- 2022/06
- 2022/05
- 2022/04
- 2022/03
- 2022/02
- 2022/01
- 2021/12
- 2021/11
- 2021/10
- 2021/09
- 2021/08
- 2021/07
- 2021/06
- 2021/05
- 2021/04
- 2021/03
- 2021/02
- 2021/01
- 2020/12
- 2020/11
- 2020/10
- 2020/09
- 2020/08
- 2020/07
- 2020/06
- 2020/05
- 2020/04
- 2020/03
- 2020/02
- 2020/01
- 2019/12
- 2019/11
- 2019/10
- 2019/09
- 2019/08
- 2019/07
- 2019/06
- 2019/05
- 2019/04
- 2019/03
- 2019/02
- 2019/01
- 2018/12
- 2018/11
- 2018/10
- 2018/09
- 2018/06
- 2018/02
- 2017/12
- 2017/11
- 2017/10
- 2017/09
- 2017/08
- 2017/07
- 2017/06
- 2017/05
- 2017/04
- 2017/03
- 2017/02
- 2017/01
- 2016/12
- 2016/11
- 2016/10
- 2016/09
- 2016/08
- 2016/07
- 2016/06
- 2016/05
- 2016/04
- 2016/03
- 2016/02
- 2016/01
- 2015/12
- 2015/11
- 2015/10
- 2015/09
- 2015/08
- 2015/07
- 2015/06
- 2015/05
- 2015/04
- 2015/03
- 2015/02
- 2015/01
- 2014/12
- 2014/11
- 2014/10
- 2014/09
- 2014/08
- 2014/07
- 2014/05
- 2014/04
- 2014/03
- 2014/02
- 2014/01
- 2013/12
- 2013/11
- 2013/10
- 2013/09
- 2013/08
- 2013/07
- 2013/06
- 2013/05
- 2013/04
- 2013/02
- 2013/01
- 2012/12
- 2012/10
- 2012/07
- 2012/04
- 2011/12
- 2011/10
- 2011/09
- 2011/05
- 2011/01
- 2010/09
- 2010/07
- 2009/12
